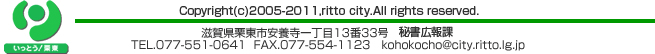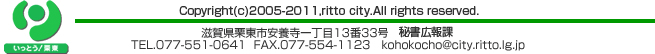江戸時代、市内を通る東海道と中山道では多くの人々や物資が行き来していました。江戸や大坂といった都市を中心に商品経済が発達してくると、農村の中にも新たな産業が見られるようになります。栗東でも、二つの街道沿いの村々などで、農作物以外のさまざまな生活物資などが加工・生産されるようになっていきました。栗東では、製薬・鋳物・藍染・醸造・しょうゆ・製糸などの産業が盛んとなっていきます。街道沿いには、これらの製品を販売する店が建ち並んでいました。その中に、旧和中散本舗をはじめとするいくつかの薬屋があります。 江戸時代、市内を通る東海道と中山道では多くの人々や物資が行き来していました。江戸や大坂といった都市を中心に商品経済が発達してくると、農村の中にも新たな産業が見られるようになります。栗東でも、二つの街道沿いの村々などで、農作物以外のさまざまな生活物資などが加工・生産されるようになっていきました。栗東では、製薬・鋳物・藍染・醸造・しょうゆ・製糸などの産業が盛んとなっていきます。街道沿いには、これらの製品を販売する店が建ち並んでいました。その中に、旧和中散本舗をはじめとするいくつかの薬屋があります。
和中散は、東海道の梅ノ木立場(栗東市六地蔵)の名物として知られた腹薬で、紀行文や道中日記、地誌などで紹介され、その名前は全国的に知られていました。江戸時代の梅ノ木立場では、複数の和中散屋が商いを競っていましたが、現在ではただ一軒「旧和中散本舗大角家住宅」(重要文化財)が当時のままの姿で残されています。
往時の和中散本舗の軒下には大きな看板が掲げられ、広い畳敷きの店先では、釜で薬湯を煎じて旅人に振る舞っていました。また、製薬は薬研や薬刀を用いて手作業で行われますが、街道からは店内に置かれた木製の巨大な製薬動輪が見られるようになっていました。これらは、販売促進のための試みということができるでしょう。
栗東の村々で売られていた薬は、和中散だけではありません。和中散と同じ梅ノ木立場の伊吹艾、手原村の仙伝虫脱丸、出庭村の万金丹、綣村の神応丸などが製造、販売されていました。現在でも、旅の途中の病気やけがは不安ですが、江戸時代の旅人たちにとっても、薬は欠かすことのできないものでした。また、軽く、かさばらず、保存がきく薬は、土産としても多くの旅人が買い求め、栗東の薬は全国へと広がっていったのです。
※栗東歴史民俗博物館では、通史展示「栗東の歴史と民俗」の中で、製薬や売薬に焦点を当てた展示を開催しています。 |