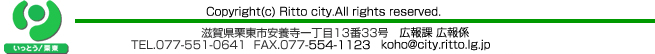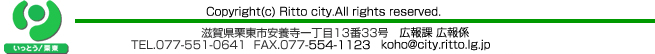|
�@�I���s�̕��암�͗鎭�R���Ɍ���������F�삪�^�y���ɂ���č��ꂽ�A���͂��̂悢���n�ł��B���n�̒[�́A�n����ʂ��������N���o���A�����Ƃ��ė��p���₷�����n�ƂȂ��Ă��܂��B�l���Z�ނ��߂ɂ��Y��Ȑ����s���ł�����A���̂悤�Ȓn�`�ɂ͏W�����`������₷���Ȃ�܂��B
�@����Љ���[��Ղ́A���̐��n�̒[���ɂ�����n��ł��B
�@�ʐ^�P�̑傫�Ȍ��́A�o�y�����╨�������i�V���I�㔼�j�Ɍ@��ꂽ���̂ƍl�����܂��B�G�������Ƃ��Ă͌`���s���ĂŁA���R�ɏo�������Ƃ��Ă͈�\�̒ꂪ�Y��ɐ��n����Ă��܂����B���̌��̐��i���s���Ă̂܂ܒ�����i�߂�ƁA�����悤�ȋK�͂̑匊���݂���܂����i�ʐ^�Q�j�B���͔���̂��̂��P���ȏ�[���A��Q���𑪂�܂����B���y����́A���q����i14���I���j�̓y���A�����̖؍ނ��o�y���A�ꂩ��͒n����������ŗ������Ƃ���A�匊�������̈�˂ł��邱�Ƃ��킩��܂����B
�@���̈�˂̒����ɂ���āA�قړ���K�͂̈�\�ł���������̑匊�̐��i���A�������̈�˂ł���Ƒz�肳��܂����B
�@����̈�ˏ�̈�\�́A����������̔��Ɍł����܂����y�w�Ō@�킪�~�߂��Ă��܂����B�����̓���ł͌@�蔲�����Ƃɑ�ϋ�J����ƍl����ꂽ�̂��A��ˌ@�肪���~����A���̌�ɓy���p�������Ƃ݂��܂��B���ӂ̒������ʂł��A����̈�\�͏��Ȃ��A�����Ȍ�̋��a�⌚���Ղ������������Ă��邱�Ƃ��A��˂��@���Ȃ��������ʁA�������Ȃ��A���Z�ɕs�K�Ȓn�ł��������Ƃ̖T�ɂȂ�܂��B�����ɂ悤�₭��˂��J��ł������ƂŁA�l�̋��Z���\�ƂȂ������Ƃ��l�����܂��B
�@�����o��܂Ŗ�P�����@���Ȃ���������̐l�X�̋�J���Â�܂����A���̖������̈�˂������������Ƃɂ��A�[�n��̏W���̕ϑJ���킩���Ă������Ƃ͑傫�Ȑ��ʂƌ�����ł��傤�B |
|
 |
�⍇��
�o�y�������Z���^�[�@TEL.553-3359�@FAX.553-3514 |
 |
|
 |
|