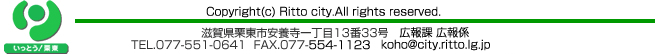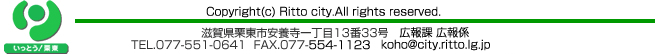�@�I�����j���������قł́A7��29��(�y)�����W�W���u���a�̂�������2023�v�W���J�Â��܂��B���̓W���́A�{�s�́u�S���Ȃ��ӂ邳�ƌI���E���a�s�s�錾�v�ɂ��ƂÂ��A�푈�ƕ��a���e�[�}�ɕ���2�N�x���J�Â��Ă�����̂ŁA�I���n��̐l����������ꂽ������p���āA�푈�����̒n��̂��炵���Č����Ă��܂��B����͂��̒�����A�푈��`�����f���h���}�Ȃǂł��Ȃ��݂́u��l�j�v���Љ�܂��B
�@��l�j�́A�����푈���瑾���m�푈�̎���i���a12�`20�N�A1937�`1945�j�ɁA�o�����m���g�s�����u���܂���v�̈��ł��B��{�̎d�l�́A�z�ɐԂ����Ō��іڂ��A����炸�ɖD�����߂����̂ŁA�����Ƃ��Đ�l�̏�������l�ɂ���̌��іڂ���邱�ƂƂ���Ă��܂����B��{�̎d�l���������Ă���f�U�C����d���ĕ��Ɍ��܂�͂Ȃ��A�I�����j���������ق̎��������i�ʐ^�Q�Ɓj�����ꂼ������������܂��B
�@��l�j�̋N���ɂ͂��낢��Ȑ�������܂����A�����m�푈���Â����I�푈�i����37�`38�N�A1904�`1905�j�̂���A�_�Ђ́u���܂���v���܂˂āA�����悯�̂܂��Ȃ���z�Ɏ��ŖD����肵�����̂����ꂽ��A��l�̒j�����u�́v�Ƃ���������z�ɏ������u��l�́v�Ƃ����u���܂���v�����ꂽ�肵�Ă������Ƃ���A����炪�����荇���Đ�l�j�����ݏo���ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B
�@���I�푈���瑾���m�푈�ɂ����Ă̎���A�R����`���Ƃ��������{�́A���O����ɐ푈�═�͏Փ˂����肩�����A���ɑ����̎�҂��������m�Ƃ��Đ��֑����A���𗎂Ƃ��Ă��܂����B��l�j�Ƃ����V�����u���܂���v�����ݏo���ꂽ�w�i�ɁA����܂ł̎���Ƃ͂����Ⴂ�̐��̎�҂����́u���v���������͖̂��炩�ł��B
�@���m�₻�̉Ƒ������̐S�̂��ǂ��낾������l�j�ł����A����Ȃ��Ƃɍ��Ƃ������߂�푈�ւ̍����������̐��ɑg�ݍ��܂�A�o���̍�@�Ƃ��Ĕ��`�������Ă��܂��܂����B�s��łȂ���Ώ�����l����̂��y�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�w�l��Ńm���}���ۂ����J�����Ƃ����̌��k���A���Ă͂悭���ɂ��܂����B
���I�����j���������كe�[�}�W�u���a�̂�������2023�v
����c7��29��(�y)����9��3��(��)�܂�
���ڍׂ͂��m�点���������������������� |