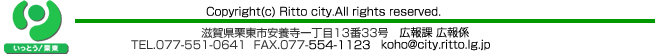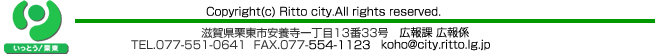第1次試験日 9月22日(日)
◆受験資格
警察官A
平成元(1989)年4月2日以降に生まれた人で、大学を卒業または令和7年3月31日までに卒業する見込みの人
警察官B
平成元(1989)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までに生まれた人で、上記警察官A区分の学歴に該当しない人
◆申込受付期間
8月1日(木)9時から8月31日(土)17時まで
◆申込み方法
インターネット(県警ホームページ「しがネット受付」)
※天災その他の不可抗力により、試験の日時、場所などを変更することがあります。最新の情報は県警ホームページでご確認ください |