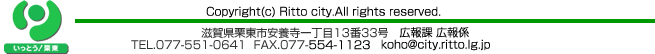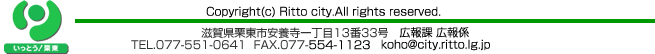明治22年(1889)の市制・町村制の施行にともない実施された「明治の大合併」は、全国で約7万あった町村を約5分の1に再編成する大規模なものでした。滋賀県内でも、1675町村が6町189村に整理されています。
一方で、近代国家の建設を急ぐ明治政府は、明治5年(1872)から7年(1874)にかけても、全国的に町村の合併を推進しています。政府の方針を受けて、滋賀県でも町村合併の手続きが行われました。明治7年(1874)に75件の合併が認可され、栗東地域でも、御園(金勝中+上山依)・高野(小坂+土+今里)・目川(東目川+西目川)・上鈎(上鈎+寺内)・苅原(半苅+市川原)の5村が成立しています。
この時期に合併が進められた理由の1つには、地租改正・地券発行といった近代的な税制への移行に向けた作業の中で、江戸時代以来複雑に入り組んだ土地の所有関係を整理するのに有意であったことが挙げられます。また、水利や祭礼で村同士が関わり合い、共同体としての関係性を築いていたという背景も見逃せません。
栗東地域からは、その後も明治8年(1875)7月から8月にかけて、15件の合併願いが提出されました(下表)。この際に合併を願い出なかったのは、前年に成立したばかりの御園を除けば小柿・上砥山・荒張の3村のみで、栗東地域の村々での合併機運の盛り上がりがうかがえます。しかし、政府は同年2月に、一転して町村合併を抑制する方針を打ち出しており、これら15件の合併も実現することはありませんでした。
この時に案として示された新たな村名には、「高辻」「川中」など旧名を合成したものや、「美栄」「豊田」など好字を用いたもの、「ヲツギ(小槻)」「梅の木」など地域の歴史にちなんだものなどがあり、合併に向けた腐心や、新たな村にかける思いが伝わってくるようです。明治の大合併に先立つこと十数年、このときの合併がいくつかでも実現していたら、その後の栗東のかたちも今とは違ったものになっていたかも知れません。
幻の明治の村
| 合併を願い出た村々 |
新たな村名の(案) |
| 東坂・井上・観音寺 |
美栄(ミエイ) |
| 下戸山・山寺(草津市) |
ヲツギ(小槻) |
| 目川・岡 |
目川 |
| 川辺・坊袋・安養寺・上鈎 |
栗本 |
| 下鈎・苅原 |
― |
| 小野・手原 |
豊田 |
| 六地蔵・大橋 |
梅の木 |
| 伊勢落・林 |
高野 |
| 出庭・千代(守山市) |
出庭 |
| 高野・辻 |
高辻 |
| 蜂屋・野尻 |
蜂屋 |
| 渋川(草津市)・中沢・笠川 |
川中 |
| 綣・霊仙寺・北中小路 |
綣 |
| 駒井沢・集・新堂(以上草津市)・十里 |
駒井 |
| 川原・平井(草津市)・小平井 |
平川原 |
『栗東の歴史』第3巻「近代・現代」より作成
■栗東町制施行70周年記念展「栗東のかたち ―明治と昭和の大合併―」
会期 11月4日(休)まで
※詳細はこちらをご覧ください |