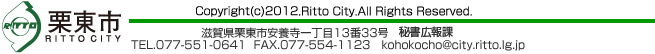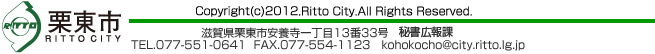高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と介護保険法に基づく「介護保険事業計画」を一体的にまとめた計画で、3年ごとに見直しをするものです。
今期の計画策定にあたっては、第4期計画における本市の高齢者福祉施策や介護保険施策の執行内容を検証し、見直しを進めてきました。
また、新たに介護保険制度改正で盛り込まれた「予防」、「介護」、「医療」、「生活支援」、「住まい」の5つのサービスを一体的に提供していく「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みを進めるにあたっては、国の基本的な指針や県の「レイカディア滋賀プラン」、本市の第五次総合計画や関連計画との整合や連携を図りながら策定しました。 |
| ○高齢者施策では、次のことを推進していきます |
①生きがいづくりと社会参加・参画ができる環境づくりとして、多様な活動の支援
②総合的な介護予防の充実として、一人ひとりが主体的にかつ継続して取り組める環境づくりと普及啓発
③高齢者の尊厳保持と権利擁護の推進として、認知症の人やその家族に対する支援や虐待防止対策の充実
④介護サービス基盤の充実として、介護を必要とする人に介護保険サービスが行き渡るサービス供給量の確保と介護サービス基盤の整備
⑤地域包括ケアの充実として、地域包括支援センターが核となり医療、介護、保健、福祉との連携を密にした適切なサービスの提供や高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる生活支援の充実
保険給付の計画では、平成24年度から3年間の要支援・要介護認定者の増加などに伴い、必要とする介護サービス提供量に応じた費用額などを見込むなかで、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、国、県ならびに市(保険者)が介護保険法で定められたそれぞれの負担割合(注:2)により拠出された財源をもって介護保険事業を運営していきます。
この中で、市は第1号被保険者に対し負担割合に相応する保険料を確保しなければならないことから、下表のとおり今期介護保険料基準額を改定します。 |
第5期(平成24~26年度)介護保険料額表
| 段 階 |
対 象 者 |
保険料基準額の調整率 |
年額保険料 |
月額保険料 |
| 第1段階 |
①生活保護受給者
②老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 |
基準額×0.50 |
29,400円 |
2,450円 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.50 |
29,400円 |
2,450円 |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 |
基準額×0.70 |
41,160円 |
3,430円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.75 |
44,100円 |
3,675円 |
| 第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.85 |
49,980円 |
4,165円 |
| 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
基準額 |
58,800円 |
4,900円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 |
基準額×1.10 |
64,680円 |
5,390円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 |
基準額×1.25 |
73,500円 |
6,125円 |
| 第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.40 |
82,320円 |
6,860円 |
| 第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 |
基準額×1.50 |
88,200円 |
7,350円 |
| 第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人 |
基準額×1.75 |
102,900円 |
8,575円 |
| 第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額×1.95 |
114,660円 |
9,555円 |
※平成24年度から26年度までの各年度における介護保険料基準額は年額58,800円(月額4,900円)です。 |
| ◎保険料基準額の上昇の要因 |
●第1号被保険者の負担割合(率)の増加
●国の介護報酬(注:3)の改定(0.7%増)および介護報酬地域区分(注:4)の見直し(本市は「その他」から「6級地」に指定され1.4~2.1%増)に伴う介護給付費の増
●前期のグループホーム整備に伴う介護給付費の増
●前期の実績に加え自然増による要支援・要介護者を見込んだサービス量に対する介護給付費の増
●制度改正により創設された介護サービスの提供および認知症高齢者の処遇改善など地域密着型サービス(注:5)の提供拡充 |
| ◎保険料基準額の適正化 |
●県財政安定化基金(注:6)返還金などの保有基金の繰り入れ
●応能負担を前提とするなかで保険料の多段階設定などを見直し、低所得者に新たな軽減措置を導入(従前の第4段階軽減に加え、第3段階に軽減を設定)
●事業の精査 |
要支援・要介護者が利用する介護サービス費用のうち自己負担となる1割分を除く介護給付費は3年間で76億7,000万円、介護予防の普及啓発や地域包括支援センター運営事業経費で2億1,000万円、併せて78億8,000万円となります。このうち2割強を第1号被保険者に負担いただくことになり、今期の保険料基準額の改定率は、平成23年度(年額51,910円、月額4,326円)対比基準額ベースで13.3%の改定増となります。
介護保険は社会全体で介護を支える制度であり、本市介護保険事業の運営にご理解、ご協力をお願いします。
注 :1【介護保険料基準額】…所得段階別保険料の設定にあたって基準となる保険料額です。
注 :2【負担割合】…第1号被保険者21%、第2号被保険者29%、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%で、第2号被保険者の保険料は市町村では徴収せず、第2号被保険者が加入する医療保険者が医療保険料として徴収します。
注 :3【介護報酬】…介護保険制度において、サービス提供事業者や介護保険施設が介護サービスを提供した場合に、その対価として支払われる報酬です。
注 :4【地域区分】…地域ごとの人件費の差を考慮して、介護報酬に乗じるものです。「1級地」から「6級地」および「その他」に区分され、区分ごとの上乗せ割合は18%~0%です。
注 :5【地域密着型サービス】…原則、市内の住民のみが利用できる介護サービスで認知症対応のデイサービスやグループホームなどです。
注 :6【県財政安定化基金】…保険者である市町村の介護保険財政の安定化に必要な費用に充て、一般会計からの繰り入れを回避するため、都道府県が設置する基金です。 |
 |
問合せ
長寿福祉課 介護保険係 TEL.551-0281 FAX.552-9320 |
 |
|