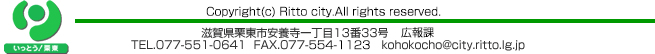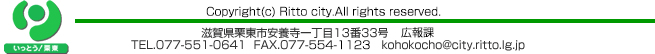今年2月から3月にかけて発掘調査を行っていた椿山古墳(古墳時代中期で滋賀県最大の帆立貝形前方後円墳)の周濠から、大阪府羽曳野市誉田御廟山古墳(応神天皇陵)出土品の次に大きい、全国最大級の笠形木製品が出土しました。 今年2月から3月にかけて発掘調査を行っていた椿山古墳(古墳時代中期で滋賀県最大の帆立貝形前方後円墳)の周濠から、大阪府羽曳野市誉田御廟山古墳(応神天皇陵)出土品の次に大きい、全国最大級の笠形木製品が出土しました。
笠形木製品はいわゆる木製埴輪と呼ばれているもので、貴人の日傘を模したものとされています。全部で6点出土し、いずれもコウヤマキという木材を使用していました。コウヤマキといえば古墳の棺桶に使用する木材として知られています。
形は中央が盛り上がった平面楕円形をしたもので、全国最大級のものは2点あります。長径76㎝・短径64㎝と、長径75㎝・短径69㎝のものです。中央にある穴は笠を立てるための柱を差し込むためのものです。大きい笠を立てるには相当な太さをもつ柱であったことが推定されます。
ちなみに笠形木製品は現在全国で313個出土しており、奈良県の出土が約7割を占め、次いで滋賀県の例が多く2割、大阪・京都合わせても1割程度しか出土していません。大きさの話にもどると、長径が70㎝以上のものは全国で6例しかなく、60㎝以上についても誉田御廟山古墳、椿山古墳、土師ニサンザイ古墳(大阪府堺市)出土の計10例しか存在しません。滋賀県の出土例では、野洲市林ノ腰古墳(全長75mの前方後円墳)から出土した約40㎝のものが最大でした。最も多いものは30~40㎝程度のものです。
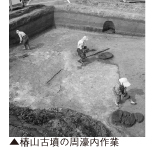 椿山古墳出土例は、大きさのほかにも内側を丁寧に円形にくり抜く技術的な特徴が誉田御廟山古墳のものと非常によく似ている点から、大王の「木製埴輪」づくりにかかわっていた集団との関連が想定できます。 椿山古墳出土例は、大きさのほかにも内側を丁寧に円形にくり抜く技術的な特徴が誉田御廟山古墳のものと非常によく似ている点から、大王の「木製埴輪」づくりにかかわっていた集団との関連が想定できます。
滋賀県の材木は都に運んでいたことで知られていますが、古墳時代から大和政権と近江の栗太郡周辺が密接につながっていたことを証明する貴重な発見であったといえます。 |
 |
問合せ
出土文化財センター TEL.553-3359 FAX.553-3514 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|