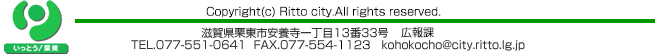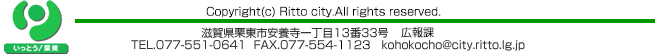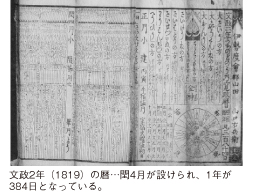 �@�������͓��퐶���ŁA���E���E��Ƃ��������Ԃ�A�t�E�āE�H�E�~�Ƃ������l�G�̈ڂ�ς����������邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȏ��Ԃ�l�G�̈ڂ�ς����A�u1���v��u1�N�v�Ƃ����P�ʂŋ�������̂��u��v�Ƃ����܂��B �@�������͓��퐶���ŁA���E���E��Ƃ��������Ԃ�A�t�E�āE�H�E�~�Ƃ������l�G�̈ڂ�ς����������邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȏ��Ԃ�l�G�̈ڂ�ς����A�u1���v��u1�N�v�Ƃ����P�ʂŋ�������̂��u��v�Ƃ����܂��B
�@���݁A���{���͂��߂Ƃ��鐢�E�̑����̍��ł́A�n�������z�̎����1��������Ԃ�1�N�Ƃ��鑾�z���p���Ă��܂��B���z��ł́A1�N�̒����͂R�U�T������{�Ƃ��A4�N��1�x�A1�N���R�U�U���ƂȂ�[�N��݂��邱�ƂŁA��Ǝ��ۂ̋G�߂̊Ԃɂ��ꂪ�����Ȃ��悤�ɏC�����������Ă��܂��B���{�ő��z��p������悤�ɂȂ����͖̂���5�N�i�P�W�V�Q�j�̂��ƂȂ̂ŁA�������j���猩��ŋ߂̂��ƂƂ�����ł��傤�B
�@���ォ�疾�����㏉���܂ł̂��悻�P�R�O�O�N�Ԃ̓��{�ł́A���̖��������̎�����1�����Ƃ��鑾�A�����{�Ƃ��A�[����݂��Ď��ۂ̋G�߂Ƃ̂�����C�����鑾�A���z��p�����Ă��܂����B����́A���A��ł�1�N�͂��悻�R�T�S���ŁA���z���1�N�Ɣ�ׂ�11���قǒZ���Ȃ邱�Ƃ���A3�N�ł��悻1�����̂��ꂪ�����Ă��܂����߁A���悻3�N��1��A�[����݂���1�N��13�����Ƃ��邱�ƂŁA���ۂ̋G�߂Ƃ̂�����C������Ƃ������̂ł��B�[����19�N��7��̃y�[�X�Ő݂����A�[����݂����N�̂��Ƃ��[�N�ƌĂт܂����B���݁A�u����v�ƌĂ���́A���̑��A���z��̂��Ƃ��w���Ă��܂��B
�@�]�ˎ���ɂ́A���N�̗�͖��{�̎��Е�s�̂��Ƃɒu���ꂽ�V���������߂Ă��܂����B�_�Ƃ���ȎY�Ƃ̂��߁A�_��Ƃ����{������������߂��ŎQ�l�ƂȂ��́A�l�тƂɂƂ��đ傫�ȊS���ƂȂ��Ă��܂������A�L����ʂɒm�炳���̂͒��O�ɂȂ��Ă��炾�����Ƃ����܂��B
�@���A���z��ł́A�]�ˎ���O���̊������N�i�P�U�U�P�j���疾��6�N�i�P�W�V�R�j�̂Q�P�R�N�ԂɂP�T�V�ʂ���̗���������Ƃ��m���Ă���A���̑g�ݍ��킹�̕��G���́A��̌���E���\�����O�ɂȂ錴���Ƃ��Ȃ��Ă��܂����B
�����j���������قł́A9��15��(�y)����J�Â�����W�W���u���̊w��v�ŁA�]�ˎ���̗��W�����܂��B
|
 |
�⍇��
�I�����j���������ف@TEL.554-2733�@FAX.554-2755 |
 |
|
 |
|
|
 |
�s���c�t���t��{�I�����K����g�ɕt���܂��傤
 �@���Ɖƒ�Ő����K���Ɋւ��鋤�ʂ̖ڕW�����߂Ď��g�ށu�����m�[�g�v�����{���Ă��܂��B�S�Ύ��́u�������炠���������悤�v�A�T�Ύ��́u�ڂ����킹�āA�傫�Ȑ��ł��������悤�v�ȂǔN��ɍ��킹���ڕW�𗧂ĂĎ��g�ނ��ƂŁA�o�~�����ȂǂɌ��C�ɂ�����������p�������Ă��܂��B�܂��A�ی�҂���́A�u���N������A���͂悤�ƌ����Ă����悤�ɂȂ�܂����v�u�ߏ��̐l�ɂ��A�傫�Ȑ��ł��������ł���悤�ɂȂ�܂����v�Ȃǂ̐������������Ă��܂��B �@���Ɖƒ�Ő����K���Ɋւ��鋤�ʂ̖ڕW�����߂Ď��g�ށu�����m�[�g�v�����{���Ă��܂��B�S�Ύ��́u�������炠���������悤�v�A�T�Ύ��́u�ڂ����킹�āA�傫�Ȑ��ł��������悤�v�ȂǔN��ɍ��킹���ڕW�𗧂ĂĎ��g�ނ��ƂŁA�o�~�����ȂǂɌ��C�ɂ�����������p�������Ă��܂��B�܂��A�ی�҂���́A�u���N������A���͂悤�ƌ����Ă����悤�ɂȂ�܂����v�u�ߏ��̐l�ɂ��A�傫�Ȑ��ł��������ł���悤�ɂȂ�܂����v�Ȃǂ̐������������Ă��܂��B
�@������A��{�I�����K�����g�ɂ��悤�u���悭�������邽�߂�12�����v�����Ɖƒ�Ŏ��g��ł��������Ǝv���܂��B |
 |
�⍇��
�c���ہ@TEL.551-0424�@FAX.551-0149 |
 |
|
|