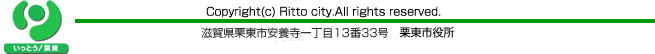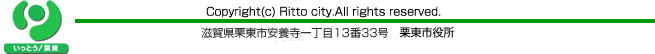| 令和7年度国民健康保険税 |
国民健康保険は、病気やけがに備えて被保険者の皆さんがお金を出し合い、医療費の補助などにあてる社会保障制度です。
滋賀県では安定的な国保運営を行うため、令和9年度から同じ所得・世帯構成であれば県内のどこに住んでも同じ保険税となるよう、保険税水準の統一化が進められています。
令和7年度の市の国民健康保険税率は、令和9年度に統一化される県標準保険税率に合わせる必要があることなどから、被保険者の税負担の軽減のため、国民健康保険特別会計の繰越金を活用した上で、次のとおり見直しを行います。 |
 |
国民健康保険税の税率と賦課限度額
区分 |
医療保険分 |
後期高齢者
支援金分 |
介護保険分 |
所得割 |
6年度 |
6.37% |
2.49% |
2.03% |
7年度 |
7.00% |
2.68% |
2.25% |
均等割 |
6年度 |
27,600円 |
10,800円 |
11,700円 |
7年度 |
29,700円 |
11,300円 |
12,100円 |
平等割 |
6年度 |
18,900円 |
7,400円 |
6,000円 |
7年度 |
20,300円 |
7,700円 |
6,100円 |
賦課
限度額 |
6年度 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
7年度 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
|
|
 |
均等割・平等割の軽減
軽減
区分 |
基準額(世帯主とその世帯に属する
被保険者の総所得金額等の合計額) |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
43万円+30.5万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
43万円+56万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1) |
|
| ※下線部分は、給与所得者等の数が2人以上のときのみ適用所得が基準額以下の世帯は、上表のように均等割・平等割が軽減されます。 |
|
|
 |
未就学児にかかる均等割額の軽減
子育て世帯の負担軽減のため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を
減額しています。※ 7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額
非自発的失業者にかかる軽減
倒産や解雇などにより離職をした65歳未満の人は、国保税が軽減されます。軽減を受けるためには、申請が必要です。
産前産後期間相当分の軽減
出産する被保険者(母親)は届け出により産前産後期間相当分の国保税が軽減されます。
※出産予定日の6か月前から届け出が可能です ※令和5年11月以降に出産した被保険者が対象です。 |
 |
| 健康寿命延伸のために |
| 日常生活で、運動や適正な食生活を心がけ、健康な生活の維持に努めることで、皆さんの継続的な医療費を削減し、国民健康保険税増税の抑制につながります。 |
特定健康診査、人間ドック
40歳以上の被保険者の人を対象に、特定健康診査を実施しています(対象者には5月下旬に通知)。人間ドックは、上限20,000円を助成しています。(対象条件があります。詳細はお問合せください)
健診や人間ドックを毎年受診することで、病気の早期発見・早期治療・重症化予防につながります。
歯科健診
歯の病気は多くの疾患に悪影響を及ぼすことが知られており、早期治療が重要です。
20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の被保険者の人を対象に、節目歯科健診を実施しています(対象者には4月下旬に通知)
かかりつけ医、かかりつけ薬局
病歴などを把握しているかかりつけの医療機関を持つことは、二重の診療を予防し、減薬に繋がります。
同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう
医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうこともあります。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の活用
新薬(先発医薬品)と同様の有効成分・効能で、新薬より低価格です。 ※変更は、医師と相談してください
マイナ保険証の活用
特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師などと共有できるほか、限度額適用認定証の発行手続きが不要になります。 |
|
 |
|