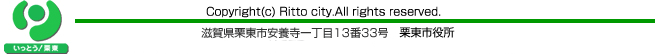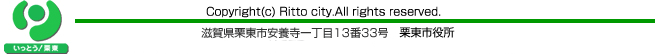絵はがきと戦争
パソコンやスマートフォンのメール機能やSNSなど、多様なコミュニケーションツールが普及した現代では、手にする機会が減りつつありますが、明治から平成時代にかけて気軽な通信手段として、また観光地のお土産として身近な存在だった「絵はがき」を紹介します。
絵はがきは明治の初めごろにドイツで誕生し、日本では明治33年(1900)に私製はがきの使用が認められて絵はがきの販売が開始されました。絵のない官製はがきに肉筆や印刷で絵を添える趣味や、はがきによる年賀状が盛んになるなど、このころ通信に新たな楽しみを求める人々の気運の高まりがあり、それが絵はがき登場の背景になったようです。こうして登場した絵はがきは、その後「戦争」との深い関わりを通じて、社会に広く定着していきます。
明治37年(1904)に日露戦争が起こり、多くの若者が兵士として中国大陸などへ送られる中、兵士と本国の家族や友人のやりとりに絵はがきは大いに利用されました。さらに逓信省(のちの郵政省)が発行した戦争に関する記念絵はがきが人々の心を捉え、絵はがきに押す記念スタンプの順番待ちで郵便局に行列ができるほどの大ブームになりました。
絵はがきと戦争、意外な取り合わせですが、多くの若者が兵士として動員された戦争への関心の高さが絵はがきを社会的に定着させました。絵はがきと戦争の関係は、日露戦争後も第一次世界大戦への参戦(1914)、シベリア出兵(1918)、満州事変(1931)、上海事変(1932)、日中戦争(1937~45)、ノモンハン事件(1939)、アジア・太平洋戦争(1941~45)と畳み掛けるように戦争が続いた40年余りの期間、変わらずに続きました。
地域の皆さんから博物館に寄贈される資料の中に時折見つかる、現在とは違った社会のありようや、当時の世界情勢を描いた絵はがきからは、長く続いた「戦争の時代」の空気と、そこに生きた人々の思いが伝わってきます。
栗東歴史民俗博物館では、栗東市の「心をつなぐふるさと栗東」平和都市宣言を受けて、開館時より戦争と平和について考えるための機会として、「平和のいしずえ」展を夏季に開催しています。
|