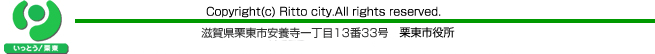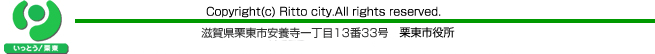平安時代の手原遺跡
手原遺跡は現在の手原駅周辺に広がる古墳時代から江戸時代にかけての複合遺跡です。今回は令和6年度に行われた発掘調査の成果をご紹介します。
これまで行われた調査によって、古代の手原遺跡には西側に寺院、そして東側には官衙(かんが)と呼ばれる役所があったことが明らかになりました。遺跡の中心部からやや南東にあたる場所で、奈良時代を中心とする大規模な掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)が多数発掘され、木簡や硯などが発見されたからです。
今回の調査では主に平安時代前半の掘立柱建物と大溝がみつかりました。掘立柱建物は東西3.5m以上、南北約3.3mの大きさで、西側は大溝と重なりあっていたため残っていませんでした。建物の向きは東西南北の正方位で、奈良時代に成立したと考えられる手原地区特有の正方位地割に沿って建てられたとみられます。幅4.3~5.5m、遺構がみつかった高さから約0.7mの深さを持つ大溝は、やや北西に向かって湾曲するものの、正方位に近い南北方向に流れていたようです。この大溝は官衙における区画溝の役割をもっていたと考えられます。
これまで手原遺跡が官衙として機能していたのは8世紀後半の奈良時代が中心と考えられてきましたが、今回の調査で整然と並ぶ掘立柱建物と区画溝が確認できたことから、後の時代である9世紀~10世紀の平安時代にも地域の中心的な役割を担う場所であった可能性が高まりました。
今後の調査でさらに手原遺跡の詳細な姿が明らかになっていくことが期待されます。 |