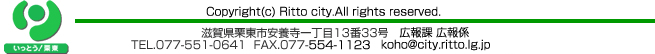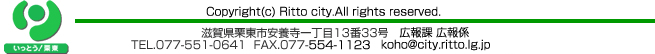|
|
 |
令和6年度国民健康保険税 |
国民健康保険は、平成30年度から県が財政運営などの中心的な役割を担っています。
市は、県が設定した標準保険税率を参考に保険税率を設定し、国民健康保険制度を運営していますが、被保険者の減少に伴う保険税収入の減少や一人あたりの医療費の増加により、歳入と歳出のバランスが取れず、安定的な運営が難しくなる恐れがあるため、令和9年度から同じ所得・世帯構成であれば県内のどこに住んでも同じ保険税となるよう保険税水準の統一化を進めています。
現在、市の保険税水準は県より低い状況であることから、被保険者の税負担の軽減のため、国民健康保険特別会計の繰越金を活用した上で、令和6年度の市の保険税率を下記のとおり見直します。 |
■国民健康保険税の税率と賦課限度額
| 区分 |
区分 |
医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
| 所得割 |
5年度 |
5.70% |
2.25% |
1.77% |
| 6年度 |
6.37% |
2.49% |
2.03% |
| 均等割 |
5年度 |
25,100円 |
10,100円 |
11,100円 |
| 6年度 |
27,600円 |
10,800円 |
11,700円 |
| 平等割 |
5年度 |
17,000円 |
6,900円 |
5,800円 |
| 6年度 |
18,900円 |
7,400円 |
6,000円 |
| 賦課限度額 |
5年度 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
| 6年度 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
※太字が変更箇所
■未就学児にかかる均等割額の軽減
子育て世帯の負担軽減のため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額しています。
※7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額
■均等割・平等割の軽減
| 軽減区分 |
基準額(世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合計額) |
| 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減 |
43万円+29.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減 |
43万円+54.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1) |
※下線部分は、給与所得者等の数が2人以上のときのみ適用
所得が基準額以下の世帯は、上表のように均等割・平等割が軽減されます。
■非自発的失業者にかかる軽減
倒産や解雇などにより離職をした65歳未満の人は、国保税が軽減されます。(申請が必要)
■産前産後期間相当分の国民健康保険税免除制度
出産する被保険者(母親)は届け出により産前産後期間相当分の国保税が免除されます。
出産予定日の6か月前から免除の届け出ができます。
※令和5年11月以降に出産した被保険者が対象 |
 |
健康寿命延伸のために |
■年1回の特定健康診査、人間ドック
40歳以上の被保険者の人を対象に特定健康診査を実施しています。(対象者には5月下旬に通知)人間ドックは、上限20,000円を助成しています。
 ■歯科健診 ■歯科健診
被保険者のうち20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の人を対象に、節目歯科健診を実施しています。(対象者には4月下旬に通知)
■かかりつけ医、かかりつけ薬局
病歴などを把握しているかかりつけの医療機関を持つことは、二重の診療を予防し、減薬に繋がります。
■ジェネリック医薬品の活用
新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能で、新薬より低価格です。 ※変更は医師に相談してください
■マイナ保険証の活用
特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できるほか、限度額適用認定証の発行手続きが不要になります。 |
 |
問合せ
国保制度や資格について
保険年金課 国民健康保険係 TEL.551-1807 FAX.553-0250
国保税の課税について
税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010
国保税の納付について
税務課 納税推進室 TEL551-0107 FAX.551-2010 |
 |
|
 |
|
|
 |
マイナンバーカード個人宅・社会福祉施設出張申請サポート |
高齢者、介護を受けている人、心身に障がいのある人などを対象に職員が自宅や入所されている社会福祉施設に訪問し、写真撮影、申請書の記入をサポートします。
実施日時 9:00~16:00(1人15分程度) ※土・日・祝、年末年始を除く
対 象 本市に住民登録がある人
必要な物 本人確認書類(下記A書類1点またはB書類2点)
A書類 運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳等の顔写真付きの身分証明書
B書類 健康保険証、介護保険証、預金通帳、年金手帳、年金証書
申込方法 実施希望日の1週間前までに、電話またはメールで申込
※カードが出来上がり次第簡易書留で送付します。カードの作成には1か月程度かかります |
マイナンバーカードによるコンビニ交付をご利用ください |
 毎日6:30~23:00まで利用できます。
※ただし、システムメンテナンスにより交付を休止する場合があります
 市役所窓口よりも100円お得に取得できます。
 マルチコピー機のある全国のコンビニで使えます。
|
「本人通知制度」 ~あなたの個人情報は大丈夫ですか?~ |
| 証明書は本人や家族が窓口で取得するのが一般的ですが、本人の委任状による代理人申請や、司法書士などの有資格者による申請などで交付することがあります。この制度を悪用して本人が知らない間に戸籍や住民票を取得し、信用調査会社などに横流しして「身元調査」に悪用する事件が発生しています。 |
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や 第三者(国または地方公共団体の機関などを除く)に交付した場合、事前登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送によりお知らせする制度です。
不正取得による個人の権利侵害の防止・抑止を目的としています。
※誰が申請したかをお知らせするものではありません |
事前登録
窓口(総合窓口課、諸証明サービスコーナー、ひだまりの家)で事前登録ができます(申込書の記入と本人確認が必要)。

オンラインでの登録は こちらから(マイナンバーカードが必要) |
 |
問合せ
総合窓口課 TEL.551-0110 FAX.553-0250 メール:[email protected] |
 |
|
 |
|
|
 |
 安土 憲彦教育長の後任として、4月1日付けで今井 義尚教育長が就任しました。 安土 憲彦教育長の後任として、4月1日付けで今井 義尚教育長が就任しました。
コメント
この度、栗東市教育長を拝命しました。教職生活42年のうち栗東高校に9年、聾話学校に2年勤務し、生徒、保護者、地域の皆さまのおかげで多くの素晴らしい経験をさせていただきました。その栗東市に今回教育長として勤めさせていただくことに大きなご縁を感じています。「栗東で育ってよかった」、「栗東で子育てができてよかった」と思っていただけるような教育の推進に、市長とともに取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
主な経歴
甲賀町立大原小学校教諭、栗東高等学校教諭、聾話学校教頭、大津商業高等学校校長、滋賀県体育協会次長などを歴任。 |
 |
問合せ
教育総務課 総務係 TEL.551-0129 FAX.551-0149 |
 |
|
 |
|
|
 |
 求職者・非正規雇用者が、就職や正規雇用を目指して資格を取得した場合、費用の一部を補助します。 求職者・非正規雇用者が、就職や正規雇用を目指して資格を取得した場合、費用の一部を補助します。
対象者
市内在住の、求職中または非正規雇用で市税を滞納していない人
対象資格
教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する講座の修了をもって取得する国家資格やそれに準ずる資格(厚生労働省ホームページ「教育訓練給付金制度 検索システム」より検索できます)
対象経費
資格取得にかかった授業料や教材費、資格などの受験料・登録料
補助金の額
対象経費の2分の1(千円未満切捨て・補助額の上限8万円)
※教育訓練給付金や公共職業訓練との併給には、要件や諸注意があります
※補助金申請は、資格取得後です
※詳細は、市ホームページに掲載
 |
 |
問合せ
商工観光労政課 労政・就労係 TEL.551-0104 FAX.551-0148 |
 |
|
 |
|
|
 |
令和2年度末の二次対策工事完了以降、対策工事の有効性の確認、環境モニタリングが実施されています。また、水処理施設の維持管理を含め、県有地化された敷地の管理が適正に行われています。
モニタリング調査結果
処分場の浸透水、周辺地下水の水質調査等は定期的に年4回実施されています。
令和5年度第3回(令和5年10月)の調査結果
●周辺地下水
自然由来のものと考えられるひ素の環境基準値超過が3地点あり、また、ほう素についても環境基準値前後で横ばい傾向にある1地点で今回超過が見られました。
●洪水調整池の水質
有害物質について環境基準の超過はありませんでした。
●硫化水素にかかる敷地境界ガス調査
全地点で不検出となっています。
※第4回目(1月)の調査結果は、県のホームページで公表され、また次回の連絡協議会で報告されます
維持管理の状況
管理委託業者および県職員による施設の点検、水処理施設の運転調整や監視が継続的に実施されており、異常などは発生していません。
今後も、周辺自治会との協定に基づき、対策工事の有効性の確認、旧処分場の安定化の確認のため、環境モニタリング等は継続されます。
※地下水などの利用にあたっては引き続き十分にご留意ください |
 |
問合せ
環境政策課 産業廃棄物対策室 TEL.551-0469 FAX.551-0148 |
 |
|
 |
|
|
 |
温室効果ガス排出量の削減やエネルギー価格の高騰などによる負担軽減のため、家庭で省エネ家電を購入した費用の一部を補助しています。
申請受付期間 令和7年2月28日(金)まで
※申込が予算枠に達した時点で受付終了
補助対象製品 ①エアコン ②冷蔵庫 ③冷凍庫
最新の省エネ基準達成率100%以上のもので、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに市内の対象店舗で購入し、購入者が居住する住宅に設置した新品に限る
対象者 本市に住民登録があり、自ら居住する市内の住宅に設置した人
※市税の滞納がない、本補助金交付要綱に定める暴力団員などに該当しないこと
補助額 購入、設置した①②③の本体価格の2分の1の額(千円未満切捨て・上限3万円)
※据付・工事の費用、リサイクル料、消費税と地方消費税の額を除く
※申請は一人(1世帯)につき、①②③のいずれか1回に限る
※詳細は市ホームページに掲載
 |
 |
問合せ
環境政策課 TEL.551-0336 FAX.551-0148 |
 |
|
 |